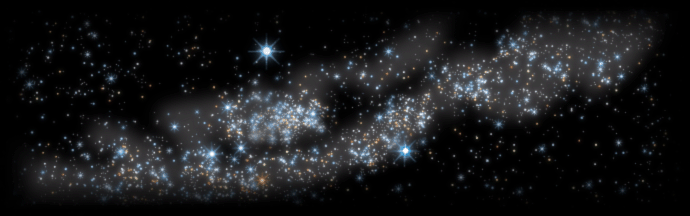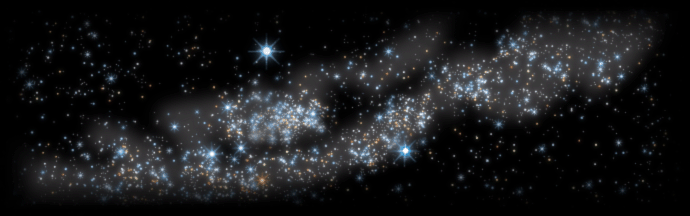トルバドゥールと姫君 ―織女と姫君の夜―
「思い出したのですが」
そう言うと、吟遊詩人は座ってリュートを爪弾いていた手をふと止めた。
「今日は東方の国で『七夕』と呼ぶ日のはずです」
「タナバタ?」
聞き慣れない発音の言葉に、敷物の上に腹這いに寝転んでリュートの音を聞いていた姫君が顔を上げた。
「ええ。昔、国に立ち寄った東方からの商人が教えてくれたのです。七月七日は『七夕』と言って、東方の国では星を祭るのだとか」
そう言うと、吟遊詩人はその星祭りの「伝説」を語り始めた。
但し、いつもの「歌」では無く本当の「語り」として。
『夜空は天の川によって東と西に分けられていて、その東側に天帝の娘で織女と呼ばれる美しい天女が住んでいた。織女は機織が上手な働き者の娘で、その織る布はとても美しく、五色に光り輝いて季節の移り変わりと共に彩りを変える不思議な布だった。織女は皆がこの布を欲しがるのが嬉しくて、一生懸命機を織り続けていた。しかし天帝は娘の働き振りに関心しつつも、年頃であるにも関わらず化粧もせずに一日中機織りばかりしている娘が不憫になり、この分では嫁にも行けないのではないかと心配して、天の川の西側に住んでいる、牛飼いで働き者の牽牛という青年と結婚させることにした。結婚した二人は、その新婚生活が楽しくて夢中になるあまり、織女は次第に機を織らなくなり、牽牛も牛飼いの仕事を忘れていった。天帝も始めは大目に見ていたが、いつまでたっても働かない二人に腹を立て、ついに二人を天の川の東と西に引き離してしまった。しかしそれではあまりに可哀想だと、年に一度七月七日の夜にだけ逢う事を許した。織女はその日を待ち焦がれて懸命に仕事に励んだが、その日雨が降ると天の川の水かさが増して、向こう岸に渡る事が出来ない。そんな二人を見かねてか、雨が降った日はどこからともなくかささぎの群れが飛んできて、川にその翼で橋を架け、二人を逢わせる手助けをしてやるのだった。その日を『七夕』と呼んで、織女星と牽牛星が出逢える日とされている』
「なかなか素敵な伝説でしょう」
にこにこと語るアレックスの話を、姫君は寝転んだ姿のままで頬杖を付いて聞いていたが、
「健気だな」
とひとこと言った。
珍しく素直なその言葉に、おやとアレックスは思い、
「健気ですね。一年に一度のその日を待って、懸命に仕事に励むなんて――」
そう言った言葉を、姫君が遮った。
「違う。『かささぎ』達が、健気だと言ったんだ」
「……」
「自業自得のせいで逢えない二人の為に、そこまで自己犠牲になってやるなんて、人がいいにも程がある。いや、鳥だから『鳥がいいにもほどがある』だな」
「……なかなか、辛辣ですね……」
「そうか?」
「何だか天帝のようにこの先姫君が嫁にも行けないのではないかと不憫で心配になってきましたよ……」
哀しげな目で自分を見るアレックスに、仏頂面で姫君は「余計な世話だ」と答えて、嫁になど行くものか、と内心で呟いた。
「『自業自得』と言うのは少々痛い言葉ですが、その通りかも知れませんね。でも一年に一度でも逢えると言う事は、私にはとても羨ましい事に思えます」
そう微笑したアレックスを見て、姫君は気が付いた。ああ、そうなのか、と。
彼は逢えない牽牛と織女を、自分の、そして『彼女』の身の上になぞらえているのだ、と。
そして「羨ましい」と言ったのだ、と。
微笑したままリュートの弦に目を遣って心を馳せていたアレックスは、突然思いもかけないその言葉を耳にした。
「お兄様」
確かに聞こえたその声が、空耳だったろうかと疑ってふと前に目を遣ると、頬杖を付いたままでこちらを見ている瞳に行き逢った。
心なしか、笑っているその唇が、先程確かにその発音を形作ったように思えて、アレックスは凝視した。
すると、その口から更に言葉が紡がれた。
「これから一日、『タナバタ』にあやかって、私が妹になってやってもいいぞ?」
にやり、とその瞳は悪戯っぽく笑っていた。
それは新しい遊びを見つけて面白がっている子供の瞳に似ていた。
それを見たアレックスはその意外な言葉にやや驚いてから苦笑し、けれどそんな気持ちの表し方が如何にもこの姫らしい、と内心で微笑した。
「本当ですか?それでは是非――」
アレックスはにこにこと嬉しげに答える。
「格好は姫君方が召される絹の裾長の衣装と珠の装飾品で、その上頭から爪先までは香を纏って、姫君らしい言葉遣いと姫君らしい立ち振る舞いと姫君らしい気品を持って一日お願いします。妹はとても淑やかでしたから。ああ、それから彼女はとても歌が上手かったで、私のリュートに合わせてよく歌っていました」
そう言うと、シャランとリュートを鳴らした。
げっ、と言う表情が、顕著に姫君の顔に表れるのを見て、アレックスはしたり顔で笑った。
「前言撤回する」とまたもや仏頂面になった姫君の様子を見て、アレックスは内心でまた微笑する。
「その代わりにお願いがあるのですが」
「何だ?」と言うように仏頂面のまま見た姫君に、アレックスは言った。
「もう一度、さっきのように呼んでみてもらえませんか」
一瞬その「さっきの」と言う言葉の指し示すものを考えていた姫君は、思い当たると、少し間のあった後に返事をした。
「――ああ、いいぞ」
そして相変わらず仏頂面で頬杖を付いたまま、
「呼んでやるから、その間目を瞑って姿でも思い浮かべて聞いてろよ」
そう言った。
アレックスが言われたようにその瞼を閉じて、懐かしい響きを耳にするのを待っていると、衣擦れの気配がして、そのすぐ後おもむろに両肩に人肌の温もりが感じられ、それが小さな手の平の感触である事がわかった時、頬にサラリと触れるものがあった。その触れたものの繊細な感覚でそれが髪だと知った時、驚いて瞼を開けようとしたアレックスの耳元で、『アスランお兄様』と囁かれた甘やかなその声に、その瞼は動く事を忘れてしまった。
囁きのすぐ後に、両肩に置かれた温もりも撫でるような髪の感触もすぐに泡のように消え去って、アレックスの耳にはその甘やかな響きの余韻だけが残された。
暫くして漸く思いだしたように開かれた瞼の下の瞳に、姿が消え去った後の部屋が映し出されていたが、しかしその心には先程与えられた余韻のせいで何も映ってはいなかった。
先程の、あれは少年などでは無く、紛う事の無い、少女だけが持つ花のような柔らかを纏った、甘い吐息だった。
長い廊下を足早に歩いて行くその姿が余りに不機嫌さを露呈していて、「どうかされましたか?」と驚いた召使が声を掛けた程だったが、
「何でもない」
と全く何でも無くは無い返事を無愛想に返して、姫君はまた廊下を歩いて行く。
そしてテラスに出ると、満点の星空を見上げ、
「――あンの、シスコン馬鹿」
と吐き出した。
本当は話をしている内に、何だかとても面白く無い気持ちになってきて、それが「もう一度呼んで欲しい」と言われた時に、一気に最高潮へと達した。そして何故だか、自分が自らの翼で橋渡しをしてやるという、あの伝説の話のかささぎになったような気がして、更に面白く無い気持ちになった。それであんな自分でも不可解な行動をとって、何かに向かって一矢報いたいと思った。
いつもの自分らしく無いこんな感情は、きっと今日が星祭りの日のせいで、あんな話を聞いたからだ、と強引に結び付けた。そしてあんな言葉を聞いてしまったから、と思った時に、そんなに腹を立てている自分に妙な気持ちになった。
何でこんなに面白く無いのだろう。
けれどその気持ちに深く立ち入る事が躊躇われて、姫君はテラスの手摺に凭れると頬杖を付いた。
夜空には東西を分けて流れる天の川が銀色に瞬いている。
その両側に、いくつもの明るい星々が輝いていたが、どれが織女で牽牛かはわからない。
ふと見た事の無い「妹」の姿が天の川の東側で待っているように思われて、けれどまだ渡るべき舟も橋も見つからずに、哀しそうに佇んでいるような気がした。
そんな事を考えている内にまた感情に心が左右されそうになって、頭を振ってそんな妄想を振り払うと、姫君は再び夜空を頬杖を付いて見つめる。晴れ渡った空には雲一つ無い。
「――逢えたんだろうか、二人?」
そう呟く姫君の耳にリュートの音が聞こえたような気がしたが、それが空耳なのか本当に聞こえたのかはわからなかった。
ただ、その音色があの吟遊詩人が側に居るようになってからというもの、姫君の心の中から消えた事は一度も無かった。
<07/07/07>
←「春の陽の君に」へ/「剣と姫君」へ→
|